銀行が最初に見る三点セット「資金使途・必要額・返済原資」の一貫性
銀行面談において、最初に必ず確認されるのが「資金使途」「必要額」「返済原資」の3点です。
これは融資審査の根幹であり、担当者が最初にチェックする「三点セット」といえます。これらが一貫していないと、どれだけ良い決算書や事業計画を持っていても、融資の可能性は大きく下がります。
資金使途は明確か
資金使途とは、融資を受けたお金を何に使うのかという具体的な用途です。
「運転資金」「設備資金」という大枠だけでなく、できるだけ詳細に説明することが重要です。
例⇨
・新規事業開始のための厨房設備購入(メーカー・見積書添付)
・仕入れ増加に伴う3か月分の運転資金(過去の仕入れ実績と比較表)
この具体性が乏しいと、銀行は「資金使途が本当に妥当なのか」を疑います。
必要額の算定根拠
必要額は、感覚ではなく計算根拠を持って提示します。
・設備資金 → 見積書、契約書、付帯費用明細
・運転資金 → 月商、仕入れ額、売掛回収期間、買掛支払期間からの計算式
例⇨
「必要額は1,000万円です」と言うだけではなく、「売掛回収が平均60日で、仕入れ支払いが30日。このギャップ分として月商500万円×2か月分=1,000万円が必要」と説明できると、説得力が増します。
返済原資の裏付け
返済原資とは、融資を受けた後、どのように返済していくかの資金の出どころです。銀行は、利益やキャッシュフローから見て返済が可能かを慎重に判断します。
・営業キャッシュフロー(経常利益+減価償却費)が返済額を上回るか
・新規事業であれば、事業計画の売上・利益予測から返済余力を算出
返済原資が曖昧だと「借りたはいいが返せない」というリスクを想定され、融資は難しくなります。
三点セットの一貫性が命
資金使途・必要額・返済原資は、それぞれ単独で説明できるだけでは不十分です。三者が整合していることが重要です。
例えば「必要額が過大で、資金使途と合っていない」「返済原資が必要額に対して不足している」といった不整合があると、即座に減額または否決の判断が下されます。
事前準備のチェックリスト
- 資金使途:明確かつ具体的か(見積書・契約書を添付)
- 必要額:根拠が数字で示せるか
- 返済原資:キャッシュフロー計算で説明できるか
- 三点の整合性:矛盾がないか
銀行は融資のプロです。感覚や勢いだけの説明はすぐに見抜かれます。
三点セットの一貫性を確保することは、銀行から「この経営者は数字に強く、資金管理ができる」と評価される第一歩です。

面談必携の書類パック「決算書・直近月次・資金繰り表・通帳」の提示順
銀行との面談において、必要書類の準備は「第一印象」を決める重要な要素です。
どれだけ経営内容が良くても、資料が揃っていなかったり提示順がバラバラだと、銀行の心証は一気に下がります。特に初回面談や融資の打診時には、「この経営者はきちんと準備している」と感じさせる書類パックを持参することが必須です。
書類パックの基本構成
面談で持参すべき書類は次の4種類が基本です。
1.決算書(3期分)
銀行は過去の業績推移を重視します。3期分を揃えて、変動点の説明ができるようにしておきましょう。
決算書は税務申告用の正式版(法人税申告書一式)を用意します。
2.直近の月次試算表
決算後半年以上経過している場合は必須。最新の数字がないと、現況の判断ができません。
売上・利益の推移だけでなく、前年同月比や累計の比較もあると説得力が増します。
3.資金繰り表(最低6か月分の予測付き)
銀行が最も注視するのは「返済能力=キャッシュフロー」です。
過去実績と今後6か月~1年の予測をセットにし、融資後の資金推移も示します。
通帳コピー(メイン口座・融資関連口座)
入出金の動きは資金管理能力のバロメーターです。
3~6か月分を用意し、資金ショートや延滞がないことを証明します。
書類は単に揃えるだけでなく、「提示順」も重要です。
銀行員が知りたい順番に並べることで、面談時間を効率化し、印象アップにつながります。
提示順の工夫で印象が変わる
~~~おすすめの提示順~~~
- 資金繰り表(今の資金状況と今後の見通しを先に見せる)
- 直近月次試算表(現状の業績を把握させる)
- 決算書(過去3期の業績推移を確認させる)
- 通帳コピー(数字の裏付けとして提出)
この順序だと、「現状→過去→裏付け」という流れになり、銀行側も理解しやすくなります。
プロは書類に“説明メモ”を添える
書類の山をそのまま渡すよりも、各資料の冒頭に1枚の説明メモをつけると、銀行の評価が格段に上がります。
・資金繰り表の見方とポイント
・月次試算表の売上・利益の特徴
・決算書の変動項目と理由
銀行は限られた時間で多くの面談をこなすため、経営者がポイントを整理してくれていると非常に助かります。
チェックリスト
- 決算書3期分を最新のものに差し替えたか
- 月次試算表は面談直前の数字に更新しているか
- 資金繰り表は予測込みで作成しているか
- 通帳コピーは記帳漏れや未処理がないか
- 資料の順番が一貫しているか
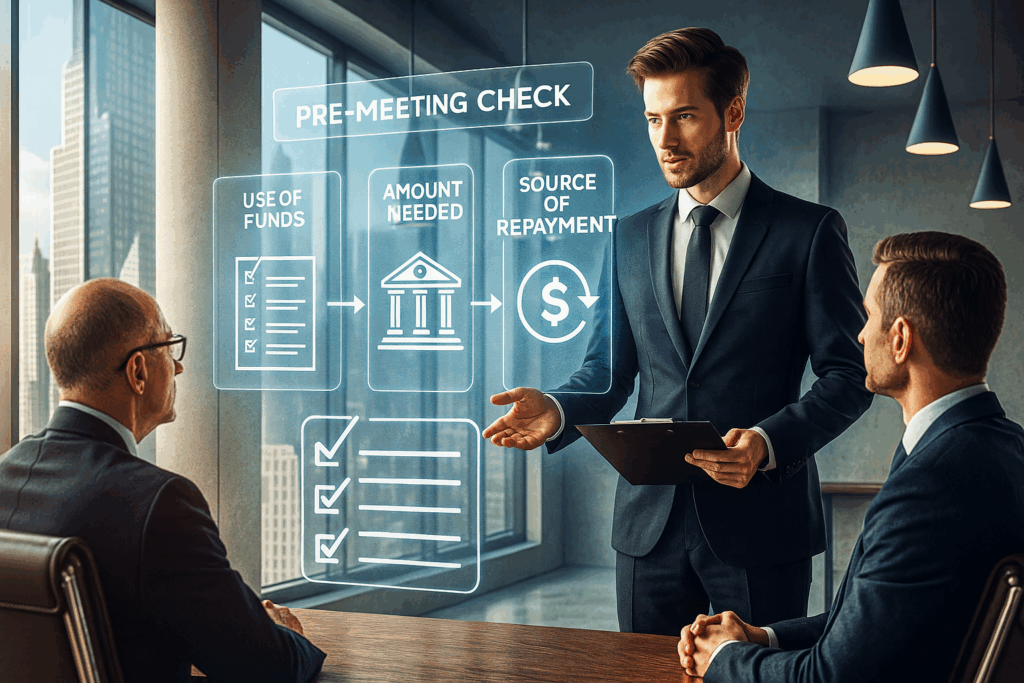
銀行は「準備ができている経営者」に融資したいと考えます。
面談時にサッと整った書類を提示できる経営者は、それだけで「管理能力が高い」と評価され、融資交渉がスムーズに進みます。
事業計画の説得力「売上仮説とKPI、受注根拠」を数字で示す
銀行は事業計画書を見るとき、「数字の裏付けがあるか」を最も重視します。
単なる希望や目標ではなく、実際にその売上を実現できる根拠を提示できなければ、計画の信頼性はゼロに等しいのです。
売上仮説の立て方
売上計画は「過去実績+改善要素」で組み立てるのが基本です。
例えば、前年の売上が1億円であれば、今年の目標1億2,000万円に至る理由を明確にする必要があります。
・新規顧客獲得数の増加(営業体制強化・広告出稿)
・既存顧客の購入頻度アップ(キャンペーン、サービス改善)
・客単価の上昇(付加価値商品の投入)
このように、売上アップの要因を分解し、それぞれの数値を算出することで、計画が「絵空事」ではなく「実行可能な仮説」に変わります。
KPI設定で計画を“測れる”形にする
銀行は「行動の進捗を測定できる指標」を求めます。
そこで重要になるのがKPI(重要業績評価指標)です。
例⇨
- 新規顧客獲得数:月50件
- 営業訪問件数:月200件
- WEB広告からの問い合わせ件数:月30件
- リピート率:60%以上
これらのKPIを達成すれば、売上目標に近づくという構造を作り、銀行に「進捗管理の仕組みがある」と印象づけます。
受注根拠を数字で示す
銀行の目線では、「売上が本当に発生するか」が最大の関心事です。
そのため、契約書・注文書・見積書・商談リストなど、将来の売上を裏付ける証拠書類を揃えて提示すると、計画の信頼性が格段に上がります。
例えば、来期の売上計画1億2,000万円のうち、既に契約済み・受注確定が6,000万円分あるとすれば、それだけで銀行は安心します。
残り6,000万円分についても、見込み案件の件数・確度を数字で説明すれば、融資判断は前向きになりやすくなります。
計画書にストーリーを持たせる
銀行は数字だけでなく、その数字に至るまでの「ストーリー」も重視します。
・どんな市場環境で
・どんな顧客に対し
・どんな強みを武器に
・どうやって売上を伸ばすのか
このストーリーが論理的かつ現実的であればあるほど、計画の信頼性は高まります。
銀行は「計画倒れの経験」を嫌う
銀行員は過去に、立派な事業計画書を持ち込んだにもかかわらず、実績が伴わなかったケースを何度も経験しています。
だからこそ、「数字の根拠があるか」「計画達成の道筋が明確か」を厳しくチェックします。
経営者側は「銀行の懐疑心」を前提に、具体的な根拠を用意して臨むべきです。
事業計画は、数字と根拠のセットで初めて説得力を持ちます。
売上仮説をKPIで裏付け、さらに受注実績や見込み案件を具体的に示すことで、銀行に「この会社なら目標を達成できる」と確信させることが可能です。
計画書は見た目や形式以上に、「数字の裏付け」と「実行の道筋」が命です。
キャッシュ循環の質「在庫・売掛・買掛」の回転と回収サイトを語れるか
銀行が融資判断で非常に重視するのが、「キャッシュフローの質」です。
単に売上や利益が出ているだけでは安心できません。
現金化のスピードが遅かったり、仕入や支払い条件が厳しければ、黒字でも資金ショートに陥る可能性があるからです。
キャッシュ循環を構成する3つの要素
- 在庫回転:仕入から販売までの期間
- 売掛回転:販売から入金までの期間
- 買掛回転:仕入から支払いまでの期間
これらのバランス次第で、同じ売上規模でも資金繰りの安定度は大きく変わります。
在庫回転の速さが資金効率を決める
在庫は売れるまで現金化できないため、過剰な在庫は資金を寝かせる原因になります。
例えば在庫回転期間が30日から60日に伸びると、その分の仕入資金が2倍必要になる計算です。
銀行に説明する際は、在庫日数の推移や在庫管理の改善策(発注サイクル短縮、売れ筋集中など)を具体的に話せると好印象です。
売掛回転と回収サイトの透明性
売掛金は「将来入ってくるはずのお金」ですが、回収が遅れれば運転資金が不足します。
銀行面談では、
・売掛金の平均回収日数
・回収サイトの分布(30日、60日、90日など)
・回収遅延の発生状況と対策
を数字で示すと、資金繰りの管理力を高く評価されます。
特に、特定取引先に売掛が集中していないかも重要です。集中度が高いと、その取引先の経営悪化が資金繰りに直撃します。
買掛回転と仕入条件交渉
買掛金は「支払いまでの猶予」を意味します。
この期間が長ければ、その分だけ資金繰りが楽になりますが、逆に短いと資金負担が増します。
銀行は「支払い条件を改善する交渉力」も評価します。
例えば、主要仕入先との契約更新時に支払サイトを30日から60日に延長できれば、その分の資金余裕が生まれます。
銀行が見ているのは「循環のバランス」
理想は、在庫回転や売掛回収よりも買掛支払いが遅い構造です。
そうすれば、入ってくるお金が出ていくお金より早くなり、資金繰りは安定します。
逆に、売掛回収より買掛支払いが早いと、常に運転資金が不足し、借入依存度が高まります。
語れる経営者は信頼される
銀行面談で、在庫・売掛・買掛の回転期間や改善策を即答できる経営者は少数派です。
だからこそ、これらの数字と改善のストーリーを語れるだけで、「資金管理能力の高い会社」と見なされ、融資交渉が有利になります。
キャッシュ循環は、会社の資金繰りの“血流”です。
在庫・売掛・買掛の回転期間を把握し、改善のための具体策を持っていることは、銀行に「この会社は資金管理がしっかりしている」と確信させます。
売上や利益だけでなく、現金の流れの健全性を示すことが、融資を引き出す鍵になります。
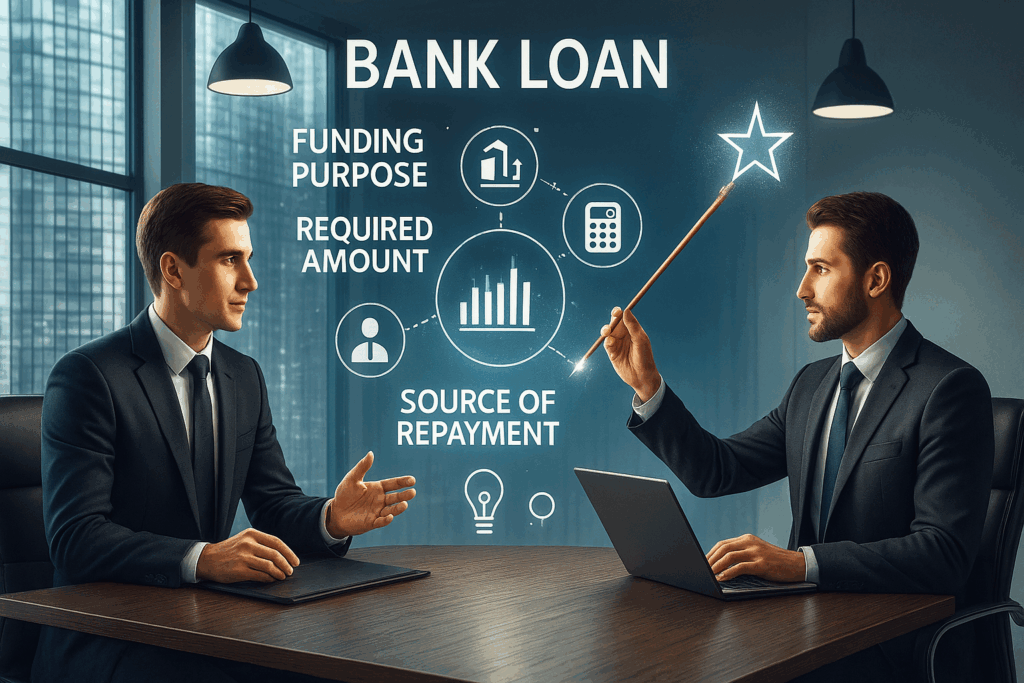
まとめ
銀行に「貸したい」と思わせる面談は、特別なテクニックではなく、準備の質と一貫性で決まります。
「資金使途・必要額・返済原資」という「三点セット」の整合性から始まり、必要書類の揃え方、事業計画の説得力、そしてキャッシュ循環の健全性まで、全てが連動している必要があります。
面談前のチェックは「筋を通す」作業
銀行が最も嫌うのは「話がその場で変わる」「数字が書類と合わない」という事態です。
それは信用の失墜につながり、たとえ融資対象としての条件を満たしていても、判断が先送りされる原因になります。
だからこそ、面談前に三点セットを整理し、提出書類の内容と整合性を取ることが最優先です。
数字を語れる経営者は強い
提出された数字や資料は、銀行員にとっては「質問の入口」です。
その質問に即答できること、しかも根拠を数字で示せることが、信用を一段高めます。
逆に「担当に任せていて詳しくはわからない」という受け答えは、経営者としての管理能力を疑われるきっかけになります。
銀行の目線を想像する
銀行員は面談中、次のようなことを頭の中でチェックしています。
- この会社の数字や説明は一貫しているか
- 将来の見通しに根拠があるか
- キャッシュの流れは安定しているか
- リスクが顕在化したときの対応力はあるか
経営者がこの「銀行のチェックリスト」を先回りして準備しておくことで、面談はスムーズに進みます。
面談は営業活動の一部
銀行との面談は、単なる融資申込みではなく「自社の魅力を売り込む営業の場」です。
つまり、金融機関に対して「この会社に貸したら安心だ」と感じさせるプレゼンの場だと捉えるべきです。
面談後に「この会社は管理がしっかりしていて、将来性もある」と思わせれば、今回の融資だけでなく、将来の追加融資や条件交渉にも好影響が及びます。
最後に
銀行は敵ではありません。むしろ、経営の安定と成長のためのパートナーです。
ただし、パートナーとして信頼を得るためには、経営者自身が数字に強くなり、準備の精度を高める必要があります。
今回の「面談前チェック10」のような視点を日常の経営に組み込み、常に貸したい会社であり続けることが、長期的な資金調達力の差になります。
外部CFO | LIFE CREATE サービス内容についてはこちらをご覧ください。




コメント