なぜ「キャッシュフロー」が最初なのか?

経営が苦しくなったとき、多くの経営者が「どうやって売上を増やすか」「どこを削減すべきか」といった損益計算書(PL)ばかりに目を向けがちです。もちろんPLの改善は重要ですが、それよりもまず先に手を打つべきはキャッシュフロー(CF)=現金の流れです。なぜなら、企業が倒産する主な理由は「赤字」ではなく、「資金ショート」だからです。
利益が出ているのに倒産する――。これは決して珍しい話ではありません。売掛金の回収が遅れたり、大型の先行投資で手元資金が枯渇したりすると、黒字でもキャッシュが回らず、結果として支払い不能に陥ることがあります。つまり、利益よりも現金の流れこそが企業の“呼吸”であり、生死を分ける分水嶺になるのです。
ここで最も重要なのは「自社の資金繰りが今どうなっているかを、具体的に把握できているか」ということです。売上がいくら、利益がいくらというのは経営指標の一部でしかありません。月末や翌月に必要な支払額と入金予定額、その差額を補うための資金はどう段取りするのか――このキャッシュフローの設計こそ、再生や改善の出発点なのです。
さらにキャッシュフローを安定させるというのは、単に資金を確保するというだけではありません。「借入金の返済計画を見直す」「長期資金で短期資金の負担を補う」「資金使途と借入のマッチングを見直す」など、構造的に資金繰りをラクにする戦略が必要です。これは単発の資金調達だけでなく、日々の出入りを見える化すること、つまり財務体制の整備にも直結します。
また、キャッシュフローの見える化が進むと、経営者自身が「次にどう動くべきか」の判断材料を得られるようになります。どのタイミングで投資すべきか、どれくらいの余力があるか、今は守りに入るべきか攻めるべきか――。感覚ではなく、数字に基づいた冷静な判断が可能になります。
このように、PL改善に走る前にまずはキャッシュの流れを整えること。これが財務改善の“正しい順番”の第一歩です。資金が足りないまま売上施策やコスト削減策を打っても、現場が疲弊するばかりで効果は薄く、逆に信用不安を招くことにもなりかねません。
キャッシュの安定がもたらす精神的余裕と経営判断
経営者にとって、手元資金の余裕は単なる「安心材料」ではありません。それは判断力の源泉であり、会社の未来を切り拓くための余白でもあります。キャッシュが尽きかけた状態では、どれほど優れた経営判断力を持っていても冷静さを保つことは難しいものです。
日々の資金繰りに追われ、「明日支払いはどこから捻出しようか」「次の給料が払えるだろうか」――そんな思考が支配する状況では、本来の“経営”に向き合う時間も気力も奪われてしまいます。
逆に、キャッシュフローにある程度の余裕ができると、目先の支払いではなく「半年後」「1年後」に必要な戦略的判断が可能になります。
たとえば、設備投資に踏み切るかどうか。新しい人材の採用や教育にコストをかけるかどうか。どれも「未来に向けた投資」ですが、資金がない中では躊躇せざるを得ません。結果として、競合に遅れをとり、チャンスを逃すという悪循環に陥ります。
この“悪循環”を断ち切るには、まずキャッシュフローの視点で余裕をつくることが第一です。そのうえで、資金使途の優先順位を整理し、「今、本当に必要な投資なのか」「先送りできる支出はないか」を見極めることが可能になります。
また、キャッシュの安定は社内の士気にも大きな影響を与えます。資金繰りが苦しいとき、従業員にもその緊張感は伝わります。場合によっては給与の遅配、支払い遅延などで外部信用が損なわれ、優秀な人材が離れていくこともあります。
一方で、経営者が資金状況を把握し、先を見通した行動をしていれば、社員も安心して自身の役割に集中できます。これは組織全体の健全化にもつながるのです。
さらに、銀行や取引先との関係性にもキャッシュの余裕はプラスに働きます。定期的な決算報告や資金繰り表の提示を通じて、相手に“見える化”された財務の安定感を伝えることで、新たな信用供与の土台が築かれていきます。
つまり、キャッシュの安定は単なる“火消し”ではなく、「攻め」の起点です。冷静な視点と選択肢を確保することで、経営者としての本来の役割――すなわち、戦略的意思決定者としての働きができるようになります。
次に着手すべきはPL改善――利益を生み出す仕組みづくり

キャッシュフローの安定化に一定のメドが立ったら、次に取り組むべきは損益計算書(PL)の改善です。ここでいう「改善」とは、単に黒字を目指すということではなく、「安定的に利益を生み出す構造へと変える」ことを指します。
PLは企業の“健康診断書”とも言える存在です。売上高、売上原価、販管費、営業利益、経常利益――この一つひとつの項目の背後には、日々の業務活動が反映されています。
だからこそ、PL改善とはすなわち、「経営の中身を変えていくこと」と言っても過言ではありません。
まず着目すべきは、粗利益率の妥当性です。売上があっても、原価率が高ければ利益は残りません。仕入先の見直しや交渉、値付けの戦略、メニューや商品構成の最適化など、粗利を確保するための“現場の努力”が必要になります。
次に、販管費のコントロールです。人件費、地代家賃、広告費などの固定費は、利益を圧迫する大きな要因になり得ます。とはいえ、単なる「削減」では会社は縮小に向かうだけ。
大切なのは、売上に直結しない“ムダ”を見極めて削るという視点です。そのためには、部門別や店舗別など、セグメントごとの利益率を分析することが有効です。
たとえば、複数店舗を運営している飲食店で、ある一店舗だけが極端に利益率が悪い場合。その理由を掘り下げていくと、人件費の過剰、在庫ロス、集客導線の不備など、“見えない課題”が明らかになることがあります。
そして何より、PL改善には「経営者が数字と向き合う習慣」が必要です。数字を見て、問題の兆候を捉え、対策を講じる。この“数字面でのPDCA”が回るようになって初めて、利益が安定して積み上がっていきます。
重要なのは、PLの改善は一朝一夕にはいかないということ。だからこそ、外部のCFOや財務コンサルといった“右腕”の存在が、経営者の判断と行動をサポートし、共に利益構造の改革に取り組むことが大きな武器となります。
PLは、「売上を上げる」「経費を下げる」というシンプルな構造の中に、無数の改善余地が潜んでいます。
そしてそれは、数字を丁寧に読み解き、現場と経営をつなぐ力があってこそ実現するのです。
BSの改善によって経営の土台を強化する
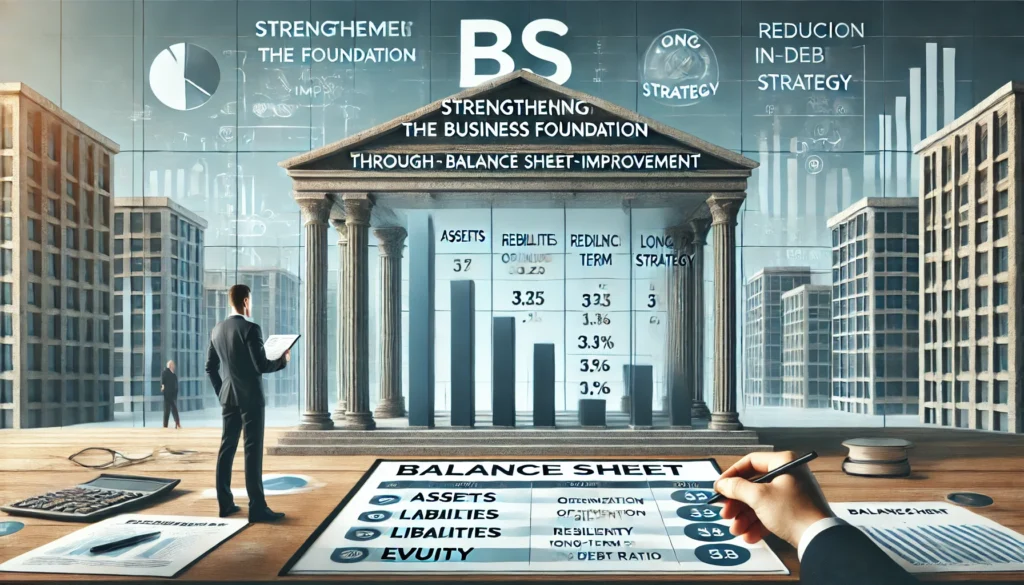
キャッシュフローの安定化、PLの改善と進んできたら、次は貸借対照表(BS:バランスシート)の改善に取り組む段階です。ここに手を入れることで、企業の経営基盤が安定し、持続的な成長や投資に耐えられる体制が整っていきます。
PLが短期的な“業績の通知表”だとすれば、BSは中長期的な“経営体質そのもの”です。
ここを見直さずに事業拡大を目指すのは、足場のぐらついた建物の上にさらに階を増築するようなものです。
まず最初に着目したいのは、「自己資本比率」です。自己資本比率が低いということは、返済義務のある借入に依存している状態。外部からの信用力が下がるだけでなく、金利負担や資金繰りにも悪影響を与えます。
借入が過剰に多い場合は、自社のBSやCFに適したリファイナンスを検討することも一つの戦略です。
次に重要なのが、「資産の質の見直し」です。
・動いていない在庫が膨らんでいないか?
・回収が遅れている売掛金はないか?
・簿価のまま残っている不要な固定資産はないか?
こういった“実態に合わない資産”がBSに積み上がっていると、経営の実力が正しく表現されないばかりか、銀行からの評価も下がってしまいます。BS改善とは、資産の整理・圧縮・入替の作業でもあるのです。
一方、負債の面でも注目すべきポイントがあります。
たとえば、長期借入金の口数が多すぎて、キャッシュフローが間に合っていない場合、このままでは資金ショートを招きかねません。
そうしたリスクを避けるためにも、BS上の「資金の出入り」と「時期」の整合性をしっかり整えることが必要です。
また、経営にとって理想的なのは、「財務の柔軟性」を持った状態です。
つまり、「借りる力が残っている」「資金調達の選択肢が複数ある」「自己資本が厚く、突発的な支出にも耐えられる」。
そのようなBSを目指すことで、将来的なM&A・新規事業・設備投資などの意思決定もスムーズになります。
このように、BS改善とは単なる数字の最適化ではなく、「経営の器を広げること」そのものです。
そしてBSは、PLの積み重ねによって形成されます。つまり、これまで改善してきたPLがしっかり利益を生み、その利益が資産・資本に蓄積されて初めて、強いBSが築かれていくのです。
数字の“見た目”を整えることに終始するのではなく、実体に伴った内容で筋肉質なバランスシートを築くこと。それが本質的な財務体質改善に直結します。
事業の持続性を高める財務戦略へ
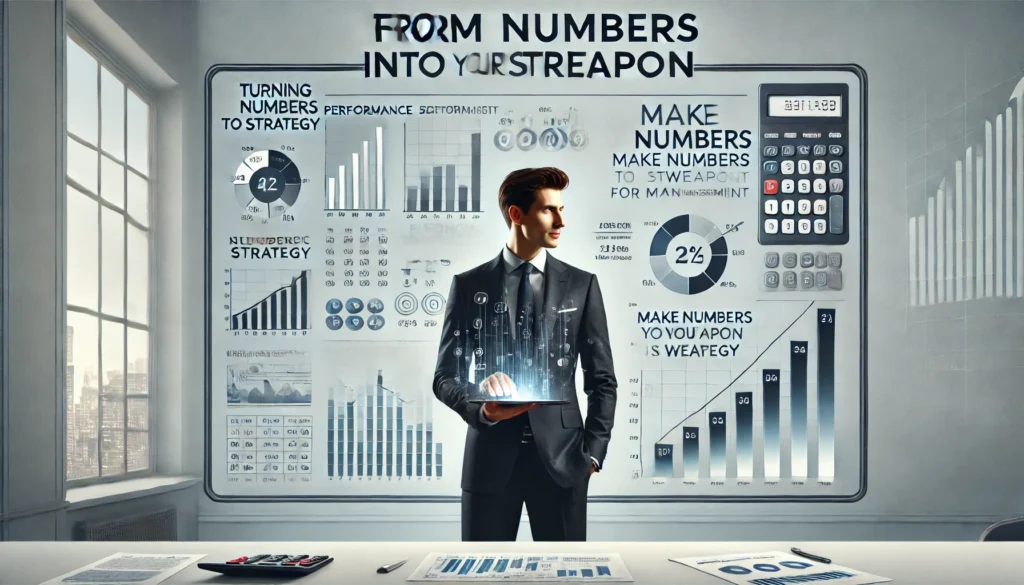
キャッシュフローの安定化、PL改善による利益確保、BSの強化と順を追って財務改善を進めることで、企業はようやく「攻めの体制」に入る準備が整います。ここから重要になるのが、「事業の持続性を高める財務戦略」です。
多くの中小企業では、「目の前の利益」や「単年度の黒字や節税」に目が向きがちですが、企業が本当に強くなるためには、継続的な成長と危機耐性の両立が求められます。
それを支えるのが、中長期的な視点に立った財務戦略です。
たとえば、設備投資や人材採用、新規事業へのチャレンジなど。どれも将来的な成長のためには不可欠ですが、同時に資金を消費する行為でもあります。
このときに、事前に資金の流れを可視化し、リスクシナリオを想定しているかどうかが、企業の命運を分けると言っても過言ではありません。
財務戦略の基本は、以下の3つに集約されます。
● 1. 投資判断のタイミングと優先順位の見極め
限られた経営資源の中で、どの投資が“最も効率よく成果を出すか”を見極めること。特に成長段階の企業にとっては、焦って投資先を広げすぎるより、「一点突破」で成果を出す方が長期的に見て効率的な場合が多いように感じます。
● 2. 財務体力の維持(調達余力・信用維持)
いくら手元資金が潤沢でも、資金調達の信用余力がなければ、いざという時に動けません。定期的に金融機関と関係性を築き、資金の引き出し口を複数確保しておくことも、重要な“見えない資産”なのです。
● 3. 非連続な危機への備え(レジリエンス)
コロナ禍や自然災害のような想定外の出来事が起こると、利益だけでなくキャッシュが一気に減ります。その時に備えた内部留保・資本政策・保険設計などが、企業のレジリエンス(回復力)を左右します。
また、社内で財務のPDCAが回っていない企業も多く見られます。
年に1回の決算だけでなく、月次ベースでの試算表の精査・キャッシュフローの予測・銀行対応のシミュレーションなど、いわば「財務の可視化と予測力の強化」が、経営の勘と経験に頼らない意思決定を可能にしていきます。
さらに、外部CFOや財務パートナーを導入することで、経営者は本来の“攻め”に専念できる環境が整います。
「売上を伸ばす」「新たな市場に挑戦する」という挑戦を、冷静な財務分析とセットで行うこと。それが今の時代に求められる“強くしなやかな経営”なのです。
まとめ 数字を「経営の武器」に変えるために

ここまで、CF→PL→BSという財務改善の正しい順番をたどってきましたが、最終的に企業が目指すべきは、「数字を経営の武器として使いこなすこと」です。
数字というのは、単なる記録ではなく、「未来を予測し、行動を変えるための羅針盤」です。
ところが、多くの中小零細企業では、試算表や決算書が税務申告のためだけに使われており、経営判断に活用されていない現実があります。
「いくら儲かってるのかわからない」「税理士に丸投げで数字は見ていない」「資金繰りが毎月ギリギリ」――そんな声が現場では頻繁に聞かれます。
これらを解消するためには、次のような“数字との向き合い方の変革”が必要です。
● 数字を見る“習慣”をつけること
月次試算表や資金繰り表を、定例で確認する文化を持つだけで、経営の感度は一気に高まります。売上や利益ではなく、「キャッシュはどうか?」「どこで無駄が発生しているか?」といった視点で数字を読み解く力が求められます。
● 数字の“構造”を理解すること
単に数値を追うだけでは不十分です。PL、BS、CFそれぞれの意味と相互関係、固定費と変動費の違い、損益分岐点の把握など、経営に直結する指標の理解が、戦略的な意思決定に繋がっていきます。
● 数字に基づいた“打ち手”を持つこと
「この数字だから、この行動を取る」という設計図を持つことが重要です。たとえば、各種利益率が悪化したらその要因を把握し具体的に・速やかに見直しへの実行ができること、資金残高が3か月分を切るなら短期融資の準備を、というように、数字とアクションを紐づける仕組みが必要です。
とはいえ、すべてを経営者自身が背負う必要はありません。むしろ、「経営者は経営に専念するために、数字の専門家とタッグを組む」ことが、これからの時代の王道といえるでしょう。
私たち株式会社ライフクリエイトは、数字に強い外部CFOとして、
・資金繰りの見える化
・財務戦略の策定
・銀行との交渉支援
・経営者の意思決定のサポート
こうした役割を通じて、「数字が苦手な経営者」を支え、「数字で強くなる経営」への進化を伴走支援しています。
財務は“守り”の領域ではなく、“攻め”を可能にする土台です。
数字を経営の武器に変え、意思決定の質を上げることこそが、持続可能な経営への第一歩。
そしてその最短ルートは、正しい順番で財務改善を進めることに他なりません。
↓具体的なサービス内容はこちらのリンクからご覧ください↓




コメント