「減価償却を飛ばして、ちょっと利益出しておきたいんだよね…」
決算前、そんな相談をされることがあります。気持ちはわかります。数字が黒字に見えた方が、銀行にも格好がつくし、取引先にも言いやすい。
でも、残念ながらその手は完全にバレています。
今回は、減価償却費の正しい意味と、なぜごまかしが通じないかを、銀行目線も踏まえて解説していきます。
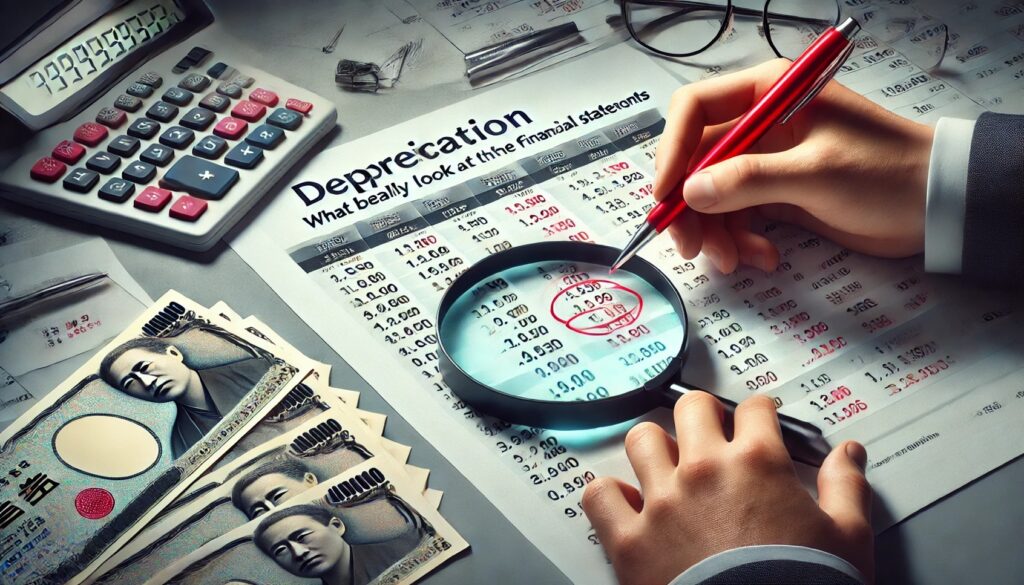
減価償却費とは?ざっくり言うと「設備の寿命を分割して経費化」
たとえば100万円のパソコンを買ったとして、1年だけ使ってポイするわけじゃないですよね?
5年くらい使うとすると、その使用年数に合わせて「毎年20万円ずつ経費として処理しましょう」という考え方。これが減価償却です。
つまり、減価償却費とは
・固定資産(建物・機械・車など)を
・複数年にわたって使用するものとして
・毎年一定額を「経費」として落としていく
という処理のこと。
そしてこれは、お金の支出はすでに終わっているけど、会計上は“少しずつ費用にしていく”という、実際のキャッシュとはズレる仕組みです。
減価償却費を飛ばすと「利益が出たように見える」という勘違い
減価償却費は、費用です。
つまり、計上しなければ利益はその分、増えます。
例えば、本来の経常利益が50万円、減価償却費が100万円あるとします。
・減価償却費をちゃんと計上:利益は ▲50万円(赤字)
・減価償却費を計上しない:利益は +50万円(黒字)
「やった!黒字だ!」と思うかもしれません。
でもこれは、紙の上の小細工にすぎません。
銀行はどこで見抜いているか?――答えは「別表16」
経営者の方はあまり見ていないかも知れませんが、税務申告の際、法人税の申告書には「別表」という箇所があります。
その中でも、銀行がよく見るのが【別表16(減価償却明細)】です。
ここには、会社が保有している全ての固定資産の情報がズラリ。
・取得年月日
・取得金額
・耐用年数
・今期の償却額
・未償却残高
つまり、「この会社、本来はこれだけ減価償却しないといけなかったのに、実際にはしてないね?」というのが、一目でわかってしまうのです。
特に銀行は「税務申告書の別表一式を提出してください」と言ってくる。
つまり、逃げ道はありません。
なぜ銀行は減価償却に厳しい?
銀行は、お金を貸す以上、「この会社は今後も返せるか?」を見ています。
そこで重要なのが、実態としてどれだけ“本当に稼げているか”という判断。
減価償却を飛ばすというのは、言ってしまえば「本当は赤字だけど、帳簿上は黒字に見せてる」状態。
むしろマイナス評価になることすらあります。
減価償却は“キャッシュを減らさない経費”。むしろ味方につけよう
もうひとつ大事なのは、減価償却はお金が出ていかない経費だということ。
つまり、会計上は利益が減るけど、手元の現金には影響しません。
そのため、キャッシュフロー計算書では、減価償却費は「プラス要素」として扱われます。
本当は“隠す”のではなく、見せて評価を上げるべき要素なのです。
減価償却を通じて見えてくる経営改善の視点
減価償却費を正しく計上していない会社は、以下のような課題が隠れているケースも。
・毎年の損益が適切に把握できていない
・設備投資の管理が甘い
・財務諸表の読み方に不安がある
・銀行対応に消極的、もしくは誤解がある
当社では、こうした「数字を整えて、銀行から信頼を得る」ためのアドバイスを日々行っています。
単に“申告するだけの数字”から、“未来につながる数字”へ。
まとめ:減価償却は“バレる”、だからこそ正しく使うべき
減価償却を計上しなかったからといって、銀行は「わからない」わけではありません。
むしろ、その裏側までしっかりチェックしています。
一時的な見せかけの利益よりも、誠実で実態に即した数字の方が、銀行からの信頼につながります。
数字の操作ではなく、数字の理解で会社の信用を積み上げましょう。
ちなみに…
銀行はPLから「減価償却費」と「税引き後当期純利益」の合計を”簡易キャッシュフロー”として、年間返済額とのバランスを見て返済できているのかできていないのかを検証する場合がありますが、これは実態のCFとは少しギャップのある手法です。
「簡易CF < 年間返済額 」となっていても、資金の流れもあるし新規借入を使っていればそれもキャッシュフローなので。
「決算書をどう見せればいいのか」「銀行にどう説明すればいいのか」など、資金調達や決算対策にお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。
本質的な財務戦略をご一緒に考えましょう。




コメント