
まずはタイプを見極める:銀行マンで変わる“提案”と“温度感”
同じ銀行でも、担当者が変われば提案も温度感も大きく変わります。
だから最初にやるべきは、相手の「型」をつかむこと。
面談の冒頭10分で、
①質問の深さ(決算のどこを掘るか)
②提案の幅(融資だけか、サービス全体か)
③意思決定プロセスの説明力(審査部や上席の視点を語れるか)を観察しましょう。
ここで“やり手”か“しぶめ”かの輪郭が見えてきます。
やり手は接触頻度が高く、成果志向で情報回収が速いタイプ。
対してしぶめは連絡が少なく、受け身で、提案よりも現状確認にとどまりがちです。
どちらが良い/悪いではなく、「こちらが主導権を持つ準備」を変えるだけ。
具体的には、
①今期の重点(売上のけん引要因・リスク)
②資金計画(使い道と回収の見立て)
③銀行にお願いしたい論点(期間、返済方法、担保の考え方)を用意し、面談前に共有。
当日はこの一枚を軸に話を進め、確認事項と次回の宿題をメモに残します。
タイプを見極め、土俵をこちらで作る——この段取りだけで、相手のペースに巻き込まれず、必要な情報だけを安全に渡せるようになります。

“やり手”を味方にする:情報の線引きと提案の選び方
やり手の銀行マンは、短期間で成果を求める分、情報の引き出しが巧みです。
ここで効くのは「情報の信号機」を決めておくこと。
緑=積極開示(公開済みの決算・方針・実績)
黄=条件付き開示(見込み案件や原価構造は守秘前提で概要のみ)
赤=非開示(競争優位や仕入先条件のコア)
面談の前に社内で線引きを合意しておけば、質問攻めでも落ち着いて対応できます。
提案の吟味は“三つの質問”で十分です。
①長期の利益に資するか(1年後の粗利に効く?)
②自由度が確保できるか(繰上げ・増額・担保の柔軟性)
③総コストは妥当か(金利+手数料+保証料+付随商品の負担)
この三点をA4一枚の「提案評価メモ」に落とし、採用・保留・見送りを明確に。
さらに、面談の最後に「次回は◯月◯日/議題は◇◇と□□」と予告面談を入れておくと、担当者は上席説明の材料を集めやすくなり、結果的にこちらの条件づくりが加速します。
やり手を“敵”にせず、“推進エンジン”として活かすことがコツです。
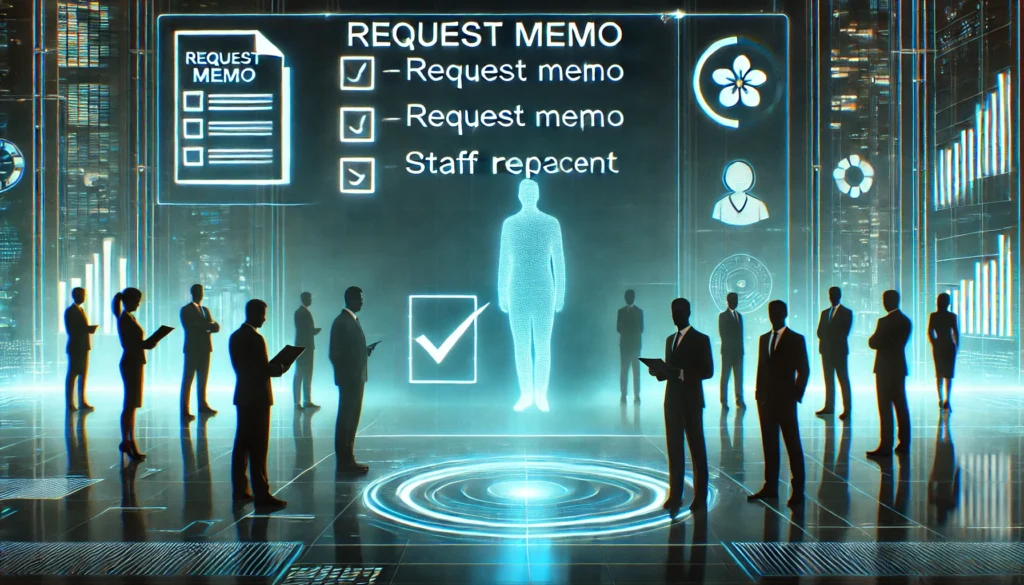
“しぶめ”を動かす:主導提案・実績提示・担当替えの選択肢
しぶめの担当者は、悪意があるわけではなく「何をどう進めればよいか」が曖昧なだけ。
受け身の相手には、こちらが台本を用意して主導しましょう。
最初に渡すのは「依頼メモ」一枚。
①希望する与信の枠・期間・返済方法
②使い道の概要と見込み
③必要な社内手続き(審査の流れ・必要書類・目安期間)
を質問形式で並べます。
次に、相手の関心を引く小さな実績を定期的に共有(受注・来店・稼働率など、前月比の“プラス”を一言)。
「前回の宿題を片づけたので次へ進ませてください」というリズムを作るのがポイントです。
それでも反応が鈍い場合は、丁寧に担当替えの道も検討します。
「御行の支援を拡大したいので、◯◯分野に明るい方をご紹介いただけますか」と前向きな理由で依頼すれば、角は立ちません。
並行して、他行の担当とも小さく関係づくりを始め、比較の視点を持つこと。
受け身の相手には、こちらが“進行役”を務める。これで、しぶめの担当でも着実に前へ動かせます。

銀行に振り回されない体制へ:対等な関係と複数行戦略
最後は体制づくりです。
担当者のタイプに関わらず、会社側が再現性のあるやり方を持てば、銀行に振り回されません。
基本は三点。
①資料の一貫性:決算・月次・申込内容・借入一覧で数字と表記を統一(端数処理や呼称も揃える)
②面談の定期化:半期ごとに予告面談を設定し、振り返り・打ち手・資金計画をA4二~三枚で先出し。サプライズをなくすほど信用は積み上がります
③複数行での分散:主力行・準主力行・情報収集行の三層で関係を育て、満期や条件を分散。
どこかが停滞しても迂回路を確保できます。
加えて、社内に金融機関連絡ログ(問い合わせ・回答・宿題・期限)を残し、属人化を防ぐこと。
最後に覚えておきたいのは、「担当者は窓口、最終判断は自社」。
提案を受けても、長期の利益・自由度・総コストの三点で静かに選ぶ。この姿勢が“対等な関係”をつくります。
自社の強みと計画を言葉にできる会社は、どのタイプの担当者とも良い関係を築けます。必要であれば、当社が面談台本作成や資料整備まで伴走します。




コメント