「今、借りるべき?」がスッと決まる判断軸
資金使途・回収計画・資金繰り余裕――3つの視点で迷いをほどく
「今、借りるべきですか?」――銀行から融資の提案が来たとき、あるいは自社で資金調達を検討するとき、最初に確認したいのは“額”や“金利”ではありません。
判断の出発点は、①資金使途の明確さ、②回収(キャッシュ創出)の見通し、③資金繰りの余裕という3つの視点です。ここが揃えば、借入のタイミングは自然と定まります。
まず①資金使途。設備更新、出店、在庫の先仕入れ、大口受注の前払コストなど、何に使い、いつまでに効果が出るのかを一行で言える状態にします。次に②回収計画。売上・粗利・稼働率・人時生産性などのKPIと回収期間(例:12〜36か月)を数字で置くことが大切。最後に③資金繰りの余裕。13週キャッシュフローで入出金を週次で並べ、追加借入後も手元資金が切れないかを確認します。
さらに実務では、以下も軽くチェックしておくと安心です。
・借入の性格(運転/設備)と返済の原資(利益・減価償却・在庫回転)
・借入一覧(残高・金利・返済額・満期・担保・保証)で満期の“山”はないか
・信用保証協会の利用枠や制度(セーフティネット・借換保証等)の残りと使い方
・金利だけでなく**総費用(手数料・保証料・繰上げ条件)**と実行スピード
小さな判断チェックを置いておきます。
- YESなら前向き検討:使途が具体/KPIと回収月数を提示できる/13週CFで資金切れがない/借入一覧で満期集中なし
- NOなら一旦見送り:使途が「とりあえず」/金利だけで選んでいる/銀行都合の月末提案に引っ張られている/保証協会枠の消耗が読めていない
借入は“攻め”にも“守り”にも使える強力な道具ですが、使途・回収・余裕の三点を押さえるだけで、迷いはぐっと減ります。次章では、創業・成長・受注・設備・出店・慢性的運転資金など、前向きに「今、借りる」が正解になる典型パターンをやさしく整理します。
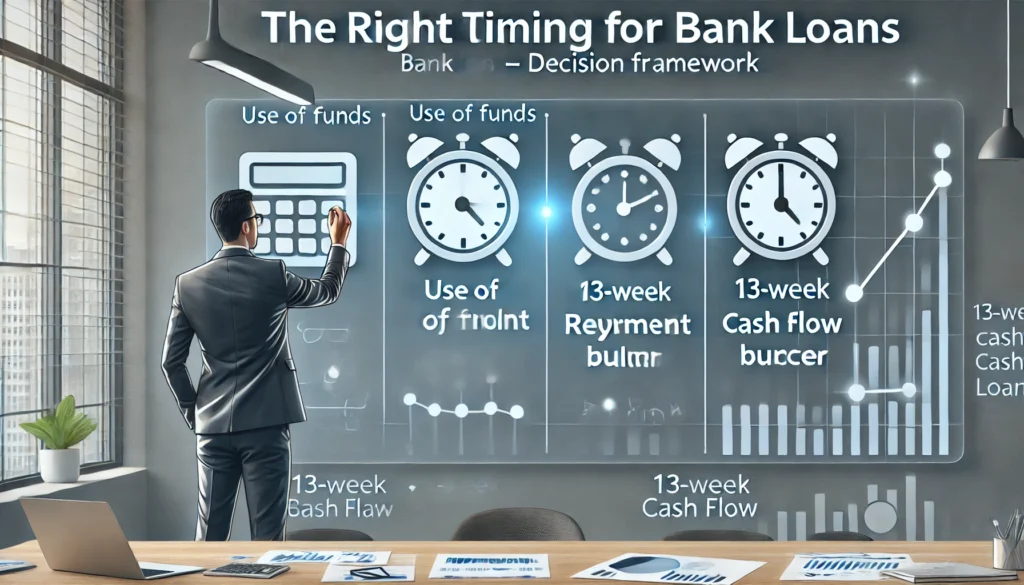
前向きに“借りる”べきタイミング
創業/売上成長/大口受注/設備投資/出店拡大/慢性的な運転資金
「借りて良い場面」は、じつは決まっています。共通点は、お金が“将来のキャッシュ”に変わる道筋が描けること。代表例をやさしく整理します。
① 創業時
開業直後は売上が立つまで時間がかかります。設備資金に加え、当面の運転資金もセットで。初期は元金返済の据置(6〜12か月)があると安心。事業計画は厚くなくてOK、「誰に・何を・いくらで・いつ回収」をA4一枚で。
② 売上が伸びる局面
仕入や人件費が先に増える“うれしい悲鳴”の時。在庫増や人員増の前倒し分を運転資金で橋渡しします。月次の数字に人時売上・在庫回転を足して、伸びの根拠を見せましょう。
③ 大口受注の獲得
材料費や外注費がまとまって発生します。入金サイトが長いと資金が詰まりやすいので、受注書・工程・支払予定を添えて前倒し調達を。可能なら**分割請求(着手金・中間金)**も同時に交渉を。
④ 設備投資(更新・増設)
長く使うものは長期で返すが原則。減価償却や生産性向上で返済原資が自然に生まれる設計かを確認。機械なら稼働率、店舗なら客数・客単価の見込みを数字で置くと伝わります。
⑤ 新規出店・事業拡大
内装や什器はもちろん、開店後3か月程度の運転資金も含めて手当てすると安全です。売上の立ち上がりは想定より遅れる前提で、最低ラインの見込みも書いておきましょう。
⑥ 慢性的に運転資金が厚い業態
製造・卸・建設など、月商の2〜3か月分を常に抱えるタイプは、短期枠や当座貸越を活用して平準化を。枠があることで、毎月の入出金の波に振り回されにくくなります。
目安として、13週CFで「借入後も資金残が切れない」こと、借入一覧で「満期の山が重ならない」ことが確認できれば、前向きな借入の準備は完了です。

“今は借りない”が正解の場面
銀行都合の提案・使途不明・信用保証協会枠の誤用に注意
借入は「いつでも多いほど安心」ではありません。今は見送るほうが賢明という場面もあります。代表的なサインをやさしく整理します。
1)銀行から“今がチャンス”と急かされるとき
月末や半期末に増える提案は、銀行側の目標事情が混ざりがち。あなたの資金需要が曖昧なまま残高を積むと、本当に必要な時に枠が空いていないという逆転現象が起きます。まずは**資金使途メモ(何に・いくら・いつ回収)**を紙1枚で作り、必要性を確かめましょう。
2)使い道が“とりあえず”のとき
「余裕資金として」「いつか使うかも」は、返済原資の設計がない状態です。借入時期をずらす/枠型(当座・手形)に留めるなど、小さく試す選択肢も。
3)金利だけで意思決定しているとき
低金利でも、保証料・事務手数料・短期回しの総コストが高くつくケースは珍しくありません。加えて、担保・個人保証・コベナンツ(約束条件)など使い勝手の条件も重要。金利<総費用×運用の自由度で比較しましょう。
4)信用保証協会の枠を把握していないとき
保証協会付き融資は枠と制度の使い分けが肝。セーフティネット・借換保証などを無計画に使うと、次回の借入や借換の余地が狭まります。まずは保証協会の利用残・制度別の使途履歴を棚卸しし、将来の選択肢を残す設計に。
5)満期の“山”が見えていないとき
借入一覧を作ると、同じ時期に満期が集中していることがよくあります。ここにさらに積むと、更新・返済の同時圧力で資金繰りが硬直化。満期が分散するよう、期間や商品を調整しましょう。
見送り判断のミニチェック
- 使途が一行で言えない/回収KPIが未設定
- 13週CFで資金残がゼロ近辺をうろうろ
- 金利だけで比較している(総コスト表がない)
- 保証協会の枠・制度の残りを把握していない
- 借入一覧で満期の山が解消できていない
どれか一つでも当てはまるなら、いったん立ち止まる勇気を。整えてからでも遅くありません。次章では、振り回されない資金調達の型(見える化と予告面談)をお伝えします。

振り回されない資金調達の型
13週CFと借入一覧で見える化、半期の予告面談、迷ったら外部CFOに相談
借入の良し悪しは「運」ではなく型で決まります。景気や銀行の事情に左右されやすいからこそ、会社側に再現性のある手順を持つことが大切です。ポイントは①見える化、②予告面談、③意思決定ルールの三本柱。
これだけで「今、借りるべき?」の迷いはぐっと減ります。
① 見える化(毎週10分)
・13週CF:入金・出金を週単位で並べ、手元資金の曲線を更新。薄くなる週に“対策メモ(支払時期の調整/在庫圧縮/短期枠)”を添えます。
・借入一覧:金融機関・残高・金利・毎月返済・満期・担保・保証・コベナンツを横並びに。満期の山に色付けし、借換や期間調整を前倒しで検討。
・保証協会の棚卸し:制度別の利用残・枠の空きを一目化。次の借入で“詰まらない”ようにルートを確保します。
② 半期に一度の“予告面談”
決算が出てからの相談は後手です。半期と第3四半期に、事前送付資料「3点セット(振り返り/今期の打ち手/資金計画)」を送り、当日は結論だけ15分→質疑→双方の宿題合意の順で。ネガティブ情報は先出し+対策で伝えると、条件改善やプロパー化の道が開けます。
③ 意思決定ルール(トリガーを決める)
・手元資金が月商0.8か月を下回る予兆 → 借入検討/支払調整を起動
・借入一覧で6か月内の満期集中 → 借換・分散の設計を開始
・保証協会枠の消化70%超 → 次の制度・プロパー比率の検討
すべての相談は、資金使途メモ(何に・いくら・いつ回収)をA4一枚で添えるのがルールです。
よくある落とし穴
金利だけで選ぶ/月次が遅れる/サプライズ報告――どれも銀行評価を下げる三大要因です。総コストと使い勝手、資料の一貫性、先回りの共有を徹底しましょう。

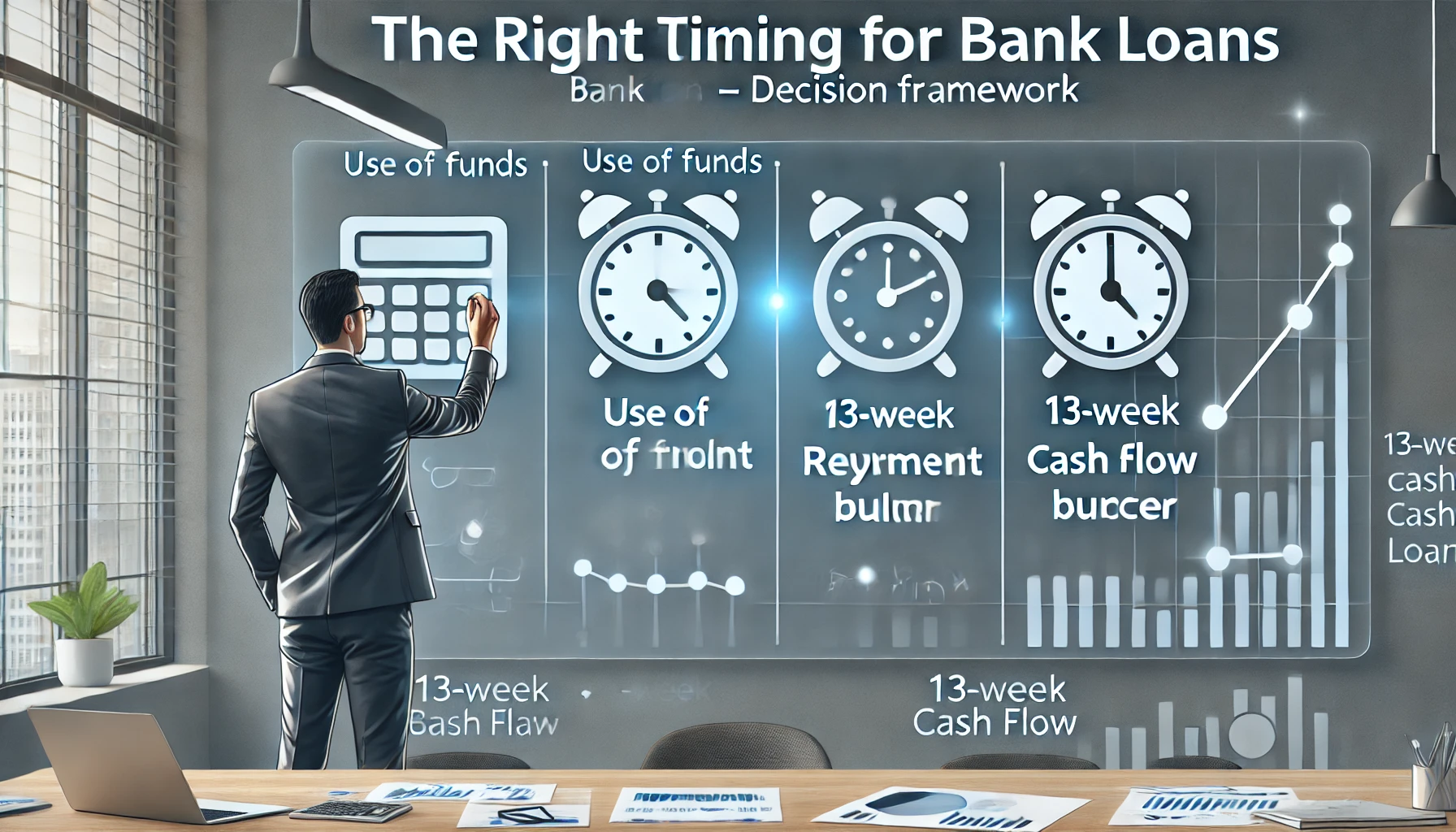



コメント