1.決算書を「提出だけ」で終わらせる危うさ
多くの中小企業では、決算期が終わると税理士が作成した決算書をそのまま銀行に提出して終わり、という流れが定着しています。
しかし、この「提出だけ」で済ませてしまう習慣には大きなリスクがあります。なぜなら、銀行が評価するのは決算書に並んだ数字そのものだけでなく、その裏にある“背景”だからです。
銀行の担当者は、決算書を読み解いて「この会社は今どんな状態か」「将来も安定して返済を続けられるか」を判断します。
もし数字の変動に説明が添えられていなければ、銀行は独自に解釈を加えます。そしてその解釈が誤っていれば、企業にとって不利な評価が下されてしまうのです。
たとえば、売上は伸びているのに利益が減少している場合
経営者の意図としては「新規店舗出店や広告投資などの先行投資を行った結果」かもしれません。
しかし説明がなければ、銀行は「売上は伸びても効率が悪化している」と判断する可能性があります。
借入が増えた場合も同様です。実際には「成長のための戦略的な借入」であっても、銀行は「資金繰りが苦しく、借入に依存している」と誤認してしまう危険があるのです。
また、在庫が大幅に増えているケース。計画的な先仕入れであり、売上増加を見越した投資行動であっても、銀行に説明がなければ「在庫が滞留し、キャッシュが寝ている」と見なされます。
このように、経営者にとって前向きな戦略的判断が、数字だけでは「リスク」として映ってしまうのです。
さらに問題なのは、銀行の評価は一度下がると回復させるのに時間がかかることです。短期的な誤解であっても、格付けや与信判断に反映されれば、以後の融資条件や取引姿勢に影響します。
言い換えれば「伝え方ひとつ」で未来の資金調達力が変わってしまうのです。
だからこそ、決算書を単なる「通信簿」として提出するのではなく、「どうしてこうなったのか」「今後どう改善・成長させるのか」を経営者自らが補足する姿勢が欠かせません。
銀行は数字の正確さだけでなく、その背景にある経営の意志や戦略を見ています。決算報告を「提出して終わり」から「説明して評価を高める場」へと捉え直すことが、経営者に求められる第一歩なのです。

2.銀行が本当に知りたい“数字の裏側”とは?
銀行は決算書の数字そのものよりも、その“動きの理由”に強い関心を持っています。なぜなら、融資判断において最も重視するのは「将来にわたって返済できるかどうか」だからです。数字は過去を示す記録にすぎません。
そこから未来を予測するために、銀行は「なぜこの数字になったのか」「今後どうなるのか」を知りたいのです。
売上が増えたのに利益が減った?
このケースはよくあります。銀行に説明がなければ「効率が悪化している」と見られがちです。しかし、実際には新規出店や広告投資などの先行投資であり、将来的に利益を押し上げる布石であることも少なくありません。
ここを明確に説明することで「戦略的な赤字」と理解してもらえます。
借入が増えている?
借入残高の増加は「資金繰りに苦しいのでは?」と見られる典型例です。けれども、経営者の意図としては「成長のための戦略的借入」であることも多いでしょう。
例えば、設備投資や新規事業の立ち上げ資金。これを「未来の収益を生むための投資」と位置づけて説明できれば、銀行の評価はまったく変わります。
在庫が急増している?
単に数字だけを見れば「在庫滞留=売れ残り」と判断されます。
しかし、繁忙期を見越した計画的な仕入れや、原材料価格高騰前の先行仕入れである場合もあります。この意図をしっかり伝えることで、銀行の誤解を防ぎ「先を読んだ経営判断」と評価されることにつながります。
銀行が知りたいのは“リスクの見える化”
結局のところ、銀行が最も気にしているのは「この会社に貸したお金は返ってくるのか?」という一点です。
そのため、数字の裏に潜むリスクや戦略を説明できるかどうかが重要になります。
悪化している数字があれば「なぜそうなったのか」「どう改善するのか」を語ること。改善が進んでいる数字があれば「どんな努力の成果なのか」を示すこと。これらを明確に伝えることで、銀行は安心し、むしろプラス評価につながります。
つまり、銀行が求めているのは“数字の事実”ではなく“数字のストーリー”です。経営者がそのストーリーを自ら語れるかどうかで、融資条件も信用度も大きく変わってくるのです。
3.信頼度を高める「補足資料」の作り方
決算報告を「提出だけ」で終わらせず、銀行の評価を高めるためには、数字の裏にあるストーリーを示す補足資料が欠かせません。
銀行は決算書に書かれた事実だけではなく、「なぜこうなったのか」「今後どうなるのか」を知りたいのです。その答えを準備するのが補足資料の役割です。
前期比較の分析レポート
もっとも基本となるのは、前期との比較資料です。売上や利益、経費の増減を単に数字で並べるのではなく、「増えた理由」「減った理由」を明確に記載します。特に悪化している項目については「改善策」や「今後の見通し」を添えることが重要です。
逆に改善された数字については「どんな努力の成果か」を伝えることで、銀行は「課題に向き合える会社」として評価を高めます。
業種特性に応じた補足データ
業種ごとに銀行が重視するポイントは異なります。
• 製造・小売業なら在庫の回転率や在庫管理体制
• BtoB企業なら売掛債権の回収状況や主要取引先の安定性
• 不動産賃貸業なら入居率や家賃収入の見通し
こうした業種特性に即した情報を添えることで、「この会社は業界の特性を理解している」と安心感を与えることができます。
組織体制・ガバナンスの見える化
中小企業では「体制が弱い」と見られることが多いため、簡易的な組織図や経理・財務管理の責任者を明確にするだけでも効果があります。
小規模であっても「誰が数字を管理しているか」が伝われば、銀行は「きちんとガバナンスを整えている会社」と受け止めます。
今期の見込みと成長戦略
銀行は過去の数字以上に「未来の見通し」を重視します。
売上や利益の計画に加え、設備投資、新規事業、人材投資など「どこに向かって会社を成長させるのか」を示すことが大切です。数字の裏にある経営者の意思を、補足資料で明確にしておくことが信頼構築につながります。
このように補足資料を整えることで、単なる「数字の提出」から「経営の意志を伝える場」へと決算報告は変わります。結果として、銀行からの評価や融資条件にも大きな差が生まれるのです。

中小企業でも実践できる“最小限ステップ”
「そんなに多くの資料を作る余裕はない…」という声を、私は現場でよく耳にします。
特に社員数が少なく、経理担当が兼務状態になっている中小企業では、決算報告用に膨大な補足資料を準備することは現実的ではありません。
しかし安心してください。すべてを完璧にそろえなくても、要点を押さえた“最小限の工夫”で銀行の評価を変えることができます。
ポイントは「紙1枚」でも十分
たとえば、売上や利益の増減理由をまとめた簡単なメモ。これはWordやExcelで表にしても良いですし、手書きの箇条書きでも構いません。
「売上増=新規顧客獲得の成果」「利益減=新店舗開業に伴う投資」など、銀行担当者が数字を理解しやすいように整理しておくだけで効果は抜群です。
在庫や売掛の内訳は口頭でもOK
在庫の増加や売掛金の残高など、決算書だけでは分かりにくい部分は、数字の内訳を口頭で説明できるようにしておくと十分です。
「在庫増=繁忙期を見越した仕入れ」「売掛増=主要取引先の売上増加に伴う一時的なもの」と説明できれば、銀行の不安を和らげることができます。
今期の計画は“箇条書き”で
銀行が最も知りたいのは「これからどうするのか」です。詳細な事業計画書を用意できなくても、「売上目標+その根拠」「コスト削減策」「人材採用や投資の予定」といった3〜5項目を箇条書きにしておくだけで、経営の意思が伝わります。
最小限でも「考えている会社」と伝わる
大切なのは資料の量や形式ではなく、「経営者が数字の意味を理解し、次の一手を考えている」ことを示すことです。銀行は「完璧な計画書」を求めているのではなく、「自社を理解している経営者かどうか」を見ています。ですから、ほんの少しの工夫で印象は大きく変わるのです。
このように、中小企業でも負担なく取り組める“最小限ステップ”を押さえることで、決算報告の質を格段に高めることができます。提出する姿勢そのものが「この会社は信頼できる」と伝わるのです。

まとめ 銀行評価を変えるのは“数字の伝え方”
決算報告は「過去の数字を提出する場」だと思われがちですが、実際には「未来の信頼を築く場」です。銀行は決算書そのものだけで企業を評価するのではなく、そこに添えられた説明や経営者の姿勢から「この会社はどんな未来を描いているのか」を見極めています。
言い換えれば、同じ決算内容でも“伝え方”ひとつで銀行の評価は大きく変わります。売上が伸びたのに利益が減った場合、それが「無計画なコスト増」なのか「将来のための投資」なのかは、説明しなければ伝わりません。借入が増えていても「資金繰りが悪化した結果」なのか「成長のための戦略的借入」なのかによって、銀行の判断はまったく逆になるのです。
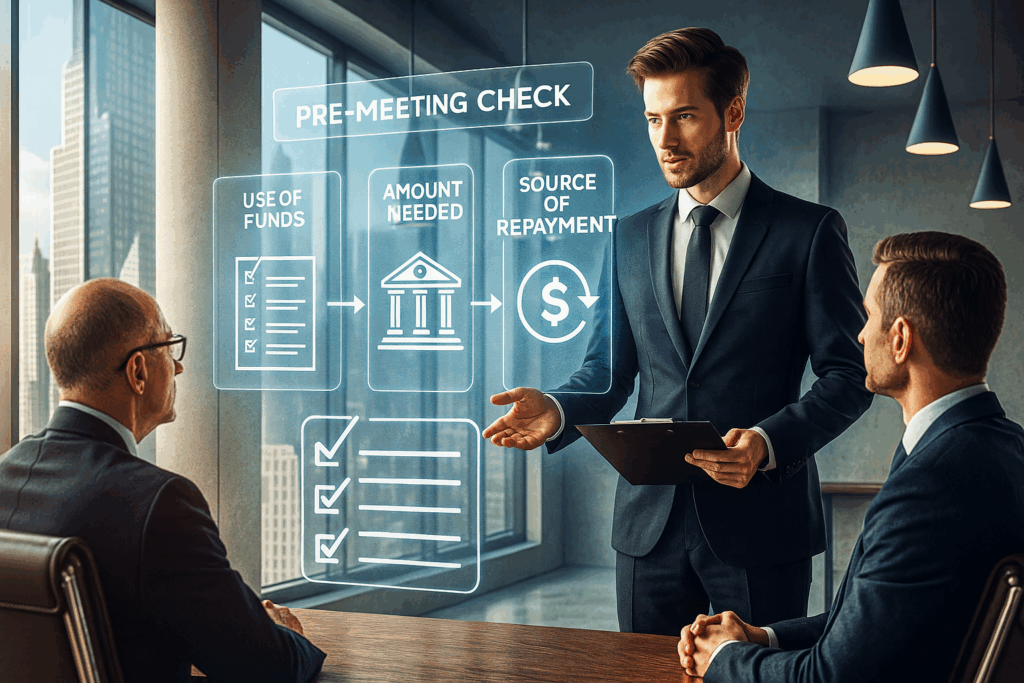
重要なのは、決算書の数字を単なる“結果”として渡すのではなく、“ストーリー”として語ること
• 前期との比較で数字の変動を説明する
• 業種の特性を踏まえて誤解を防ぐ
• ガバナンスや管理体制を示して信頼を得る
• 将来の計画を提示して成長性を印象づける
こうした工夫を積み重ねることで、銀行からの評価は確実に変わります。
特に中小企業の場合、経営者自身の言葉と姿勢が与える印象は大きな影響を持ちます。決算説明において「数字を把握している」「改善に取り組んでいる」「未来を描いている」と感じさせることができれば、それだけで融資条件や信用枠の拡大につながる可能性が高まるのです。
もし「どう説明すればいいか分からない」「資料を整える余裕がない」と感じるのであれば、外部の支援を活用するのも一つの方法です。外部CFOや財務コンサルが同席し、資料作成や説明補足を行うだけでも、銀行との関係は劇的に変わります。
決算報告は単なる義務ではなく、未来への投資です。数字の伝え方を工夫することで、銀行からの信頼を獲得し、次の成長資金を引き寄せることができます。経営者がその意識を持つことこそ、資金調達力を高め、会社の未来を切り開く第一歩なのです。
外部CFO | LIFE CREATE サービス内容についてはこちらをご覧ください。




コメント