人手不足と人件費削減要請の板挟み
「人を入れなければ現場が回らない」
「でも利益を出すには人件費を削らなければならない」
こうした矛盾に悩む中小企業経営者は非常に多いのが現実です。現場は人手不足で悲鳴をあげているのに、決算書上では人件費率が高すぎて銀行や投資家からの評価が下がる。まさに板挟みの状況に置かれているのです。
背景には、人件費が企業にとって最大級の固定費であることが挙げられます。飲食、サービス、小売、介護といった労働集約型の業種では、人がいなければ売上が立たない一方で、売上が落ちても人件費は翌月すぐに削減できません。
最低賃金の上昇も続き、パート・アルバイトにかかるコストも年々増加。
さらに優秀な人材を確保しようとすれば、給与や福利厚生など追加の負担も避けられません。
この結果、売上が伸びないのに人件費が膨らみ、PL上の人件費率は上昇します。人件費率が高止まりすると、金融機関から「経営効率が悪い」と判断され、新規融資の条件が悪化したり、時には融資が受けられなくなるリスクもあります。
つまり、現場を守るために人を増やせば財務評価が下がり、財務評価を守るために人を減らせば現場が回らなくなる。
どちらを選んでも経営に打撃を与えかねない難しいジレンマに陥るのです。
この矛盾を解決するには、まず「人件費は単なるコストではなく投資でもある」という視点を取り戻すことが欠かせません。
人件費を減らすことだけにとらわれるのではなく、
「人件費をどう活かすか」
「どうすれば同じ人数でより大きな成果を出せるか」
という問いにシフトする必要があります。
つまり、板挟みに見える状況も、見方を変えれば「経営の構造を見直すチャンス」なのです。
経営者がまず取り組むべきは、「自社にとって人件費がどのような構造になっているのか」を明確にすることです。どの部門で人件費が膨らんでいるのか、正社員・パート・外注のバランスは適正か、売上との連動性はどうか。数字を分解して初めて、どこを守り、どこを見直すべきかが見えてきます。
矛盾に見える課題を真正面から受け止めることで、経営は一歩前に進みます。人手不足と人件費削減要請という二律背反に悩むのではなく、「どうすれば人を活かしながら人件費率を改善できるか」という発想の転換が、経営者に求められる第一歩なのです。
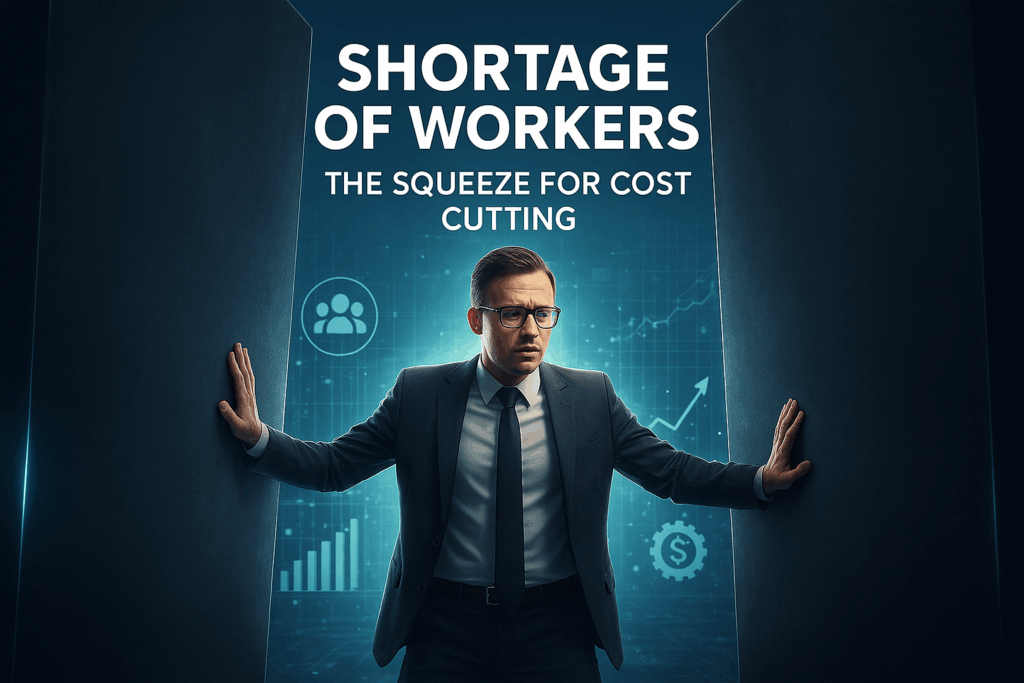
人件費はコストか投資か?経営判断のズレ
中小企業経営における最大の誤解のひとつが「人件費=削るべきコスト」という考え方です。確かに会計上、人件費は損益計算書に「販売費および一般管理費」として計上され、利益を圧迫する要因として扱われます。
そのため、赤字や資金繰り悪化に直面すると、経営者はまず「人件費を下げなければ」と考えてしまうのです。
しかし、人件費の本質は「未来への投資」です。人を雇い、育て、定着させることで企業は継続的に利益を生み出す力を強化できます。新しい人材が入ることで業務が効率化され、サービスの幅が広がり、顧客満足度が向上する。教育や研修は即効性こそありませんが、数年先には大きなリターンをもたらします。それでも会計上は「経費」としか見なされないため、銀行や投資家の評価は「短期的に利益を圧迫している」となり、ここに大きなズレが生じるのです。
たとえば、社員教育のために研修を実施すれば、その費用はすべて経費計上されます。採用のための広告費も、福利厚生のための手当も同じ扱いです。経営者が「これは将来の利益を生むための投資だ」と信じても、PLには「今期の利益を減らすコスト」として数字が並びます。
つまり、長期的視点と短期的評価の間に、どうしてもギャップが発生してしまうのです。
このギャップは、経営判断を誤らせる大きな要因となります。銀行や外部の専門家から「人件費率を下げろ」と指摘されると、多くの経営者は人材削減や給与抑制といった短期的施策に走りがちです。しかし、それでは現場の力が落ち、売上やサービス力が低下し、結局は長期的に収益を失うことになります。
人件費を「削る」方向でしか捉えないことが、企業の競争力を削ぐ最大の要因となるのです。
本当に必要なのは「人件費をコストではなく投資として設計し直す」視点
人件費が未来の利益を生む仕組みをどう作るか。どの部分は削ってよい支出なのか、どの部分は絶対に守るべき投資なのか。その仕分けを行うことで、初めて人件費は「重荷」から「武器」へと変わります。
つまり、人件費をどう見なすかは単なる会計処理の問題ではなく、経営の本質に関わる戦略的な選択なのです。
削る発想から“活かす”発想へ 3つの実践アプローチ
人件費を考えるとき、多くの経営者がまず思い浮かべるのは「削る」という発想です。赤字や資金繰りの悪化に直面すると、どうしても人件費削減=人員削減に意識が向きがちです。
しかし、人手不足が常態化している今の日本で、単純に人を減らせば現場の負担は増し、サービスや品質は低下し、結果として売上や顧客満足度を損ねることになりかねません。求められているのは「削る」ではなく「活かす」発想です。ここでは、そのための3つの実践アプローチを紹介します。
① 人時売上高の改善で生産性を上げる
人件費率は「人件費 ÷ 売上高」で決まりますが、この式を「1時間当たりの売上」に分解して考えると改善の余地が見えます。
たとえば、同じ人件費でも1時間あたり3,000円の売上を出す店舗と5,000円を出す店舗では効率が全く違います。シフト設計の見直しや、動線改善による無駄削減、受発注や会計システムの導入で業務を短縮すれば、人数を減らさずに人件費率を下げることが可能です。
② 売上の底上げで“分母”を増やす
人件費率を下げるもう一つの方法は、売上の底上げです。客単価を上げたり、集客数を増やしたりすることで、分母となる売上が増えれば自然に人件費率は下がります。たとえば、セット販売やアップセル、SNSを活用した集客施策、リピート率を高めるキャンペーン、さらにはサブスクや回数券の導入などが有効です。
人を減らさず「稼ぐ力」を高めることで、健全な改善につながります。
③ 業務の効率化と一部外部化
すべての仕事を社員やアルバイトで抱える必要はありません。
定型業務はITや外注に任せ、従業員が“人でしかできない価値ある仕事”に集中できるようにすることが大切です。たとえば、シフト管理や勤怠はクラウドで、経理や給与計算は外部に委託、店舗ならセルフレジやモバイルオーダーを導入するなど。初期投資はかかりますが、中長期的には人件費率を安定させ、働きやすい環境をつくります。
この3つのアプローチに共通しているのは「人件費を減らすのではなく、人の力をどう活かすか」という視点です。
削ることばかりに目を向けるのではなく、効率を上げ、売上を伸ばし、仕組みを整えることで、人件費は重荷から成長の原動力へと変わります。
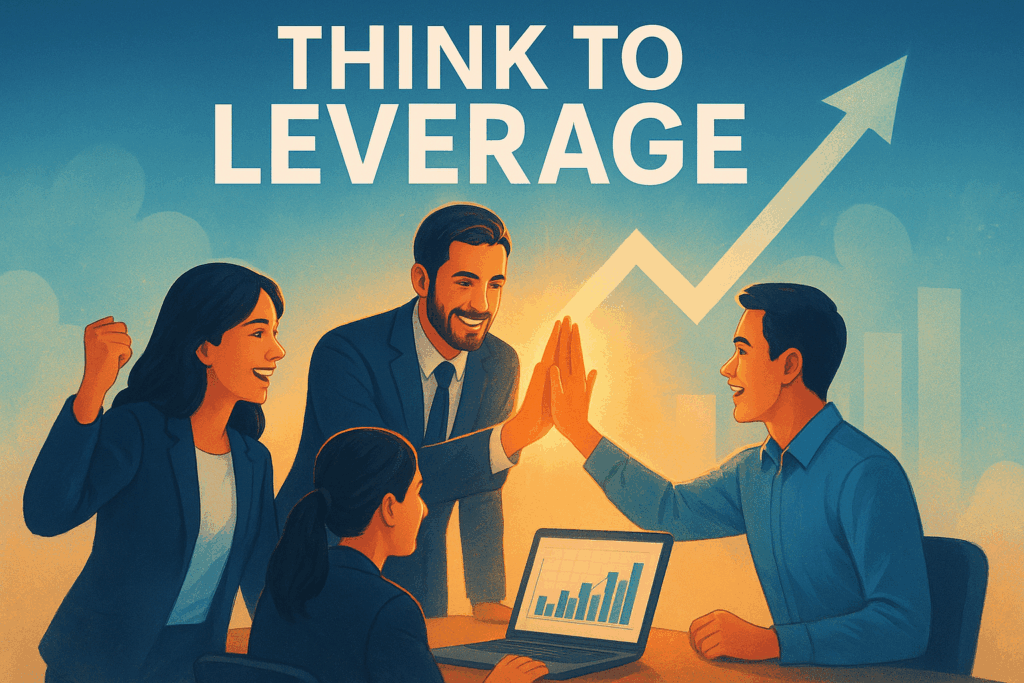
人件費の“見える化”と最適バランス
人件費の改善に取り組む際、最初にやるべきことは「見える化」です。数字が曖昧なままでは「削るべきか、増やすべきか」の判断を誤ります。見える化とは単に総額を把握するのではなく、内訳を分解して「どの人件費が固定費で、どの人件費が変動費なのか」を明らかにすることです。
例えば、正社員の給与は固定費、パートやアルバイトの給与は変動費として整理できます。さらに外注費や業務委託費も、変動費として扱うことが可能です。直接部門と間接部門の人件費割合を明確にすることで、「利益を生む現場」にどの程度コストが割かれているかが見えるようになります。
これを行わずに「人件費が高いから削る」と判断するのは、経営判断の精度を大きく落とす原因になります。
では、どのようなバランスが理想的なのでしょうか。
業種や企業規模によって最適解は異なりますが、一般的には 正社員40%、パート・アルバイト35%、外注25% という構成がひとつの目安になります。
この比率であれば、固定費を抑えつつ、繁閑差に応じた柔軟な人材配置が可能です。たとえば繁忙期はパートを増やし、閑散期は外注に切り替えることで、無駄な人件費を抱え込まずに済みます。
しかし、ここで忘れてはならないのが「現場の納得感」です。
数字上は効率的でも、社員にとって「なぜ配置転換するのか」「なぜ外注に任せるのか」が説明されなければ、不信感が募り離職につながりかねません。人件費の最適化は合理化ではなく「合意形成のプロセス」がカギを握ります。経営者が背景を丁寧に伝え、労働条件や評価制度を共有しながら進めることで、現場に安心感と協力姿勢が生まれます。
人件費の見直しは、単に数字をいじる作業ではなく、経営と現場をつなぐコミュニケーションそのものです。
構成を見える化し、最適バランスを設計し、納得感を持って運用する。この3つが揃って初めて、人件費は経営を支える武器となります。
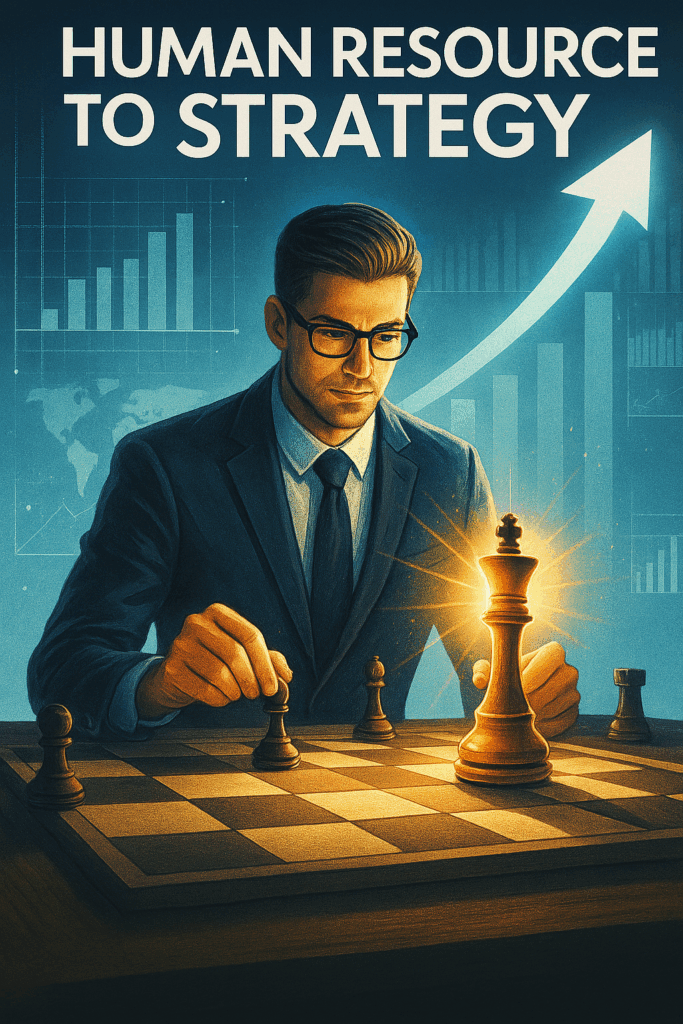
人件費を“経費”から“戦略”へ
人件費は企業にとって最大の支出でありながら、最大の投資対象でもあります。しかし、多くの経営者は会計上の見え方に引っ張られ、「人件費=コスト」としか捉えていません。ここにこそ、経営の伸びしろがあります。
人件費を単なる経費として扱えば、「どう削るか」という発想に陥りがちです。しかし、経営に必要なのは「どう活かすか」という発想です。つまり、人件費を“経費”から“戦略”へと位置付け直すこと。これができるかどうかで、会社の未来は大きく変わります。
まず重要なのは、正社員・パート・外注の比率を戦略的に設計すること
正社員にしかできない中核業務はしっかり任せる一方、繁閑差が大きい業務や定型的な業務はパートや外注に委ねる。これにより、固定費に偏らず、変動費を活かした柔軟な体制を築けます。
さらに、評価制度と人件費を連動させることも欠かせません。「人件費を払う=雇用を維持するため」ではなく、「成果やスキルに応じて投資する」という仕組みをつくることで、社員に納得感が生まれます。納得感は定着率を高め、長期的な人材育成につながります。人件費を単なる支出ではなく「未来の利益創出の原資」として設計するのです。
加えて、銀行評価まで視野に入れた設計が求められます。金融機関は人件費率だけを見ているのではなく、その内訳や構造のバランスを見ています。つまり「人件費率が高い=即NG」ではなく、「高いが合理的な理由がある=むしろ積極評価」もあり得ます。自社の戦略と数字をリンクさせ、説明できるように整えておくことが、金融機関からの信頼につながります。

人件費は企業の未来を形づくる最大のレバーです。
削るだけではなく「設計する」「戦略に組み込む」ことで、会社は柔軟で強い体質へと変わっていきます。人手不足が常態化する時代だからこそ、「人を減らす」ではなく「人を活かす」。
この転換こそが、持続的な成長を実現するための最重要テーマなのです。
外部CFO | LIFE CREATE サービス内容についてはこちらをご覧ください。




コメント