建設業で初めて融資を使う場合、最初に「長期借入金」で設備投資やスタートアップ資金をまとめて調達するのが一般的です。特に重機や大型工具、現場の立ち上げ費用など、一発の支出が大きいので、返済計画を見据えた長期借入が妥当。しかし、実際の現場運営では、それだけでは足りない局面が必ず出てきます。

■ 長期借入の特徴と使いどころ
長期借入金は、通常数年から10年以上の返済計画を前提にした借入です。金利も比較的低く、返済額が月々一定になるため、事業計画に組み込みやすいというメリットがあります。新設物件への初期投資や大型機器導入に向いていて、設備のライフサイクルと融資期間がマッチするのも◎。
ただし、現場は常に動いています。受注件数や売上発生のタイミングが偏ると、当初の資金計画からずれてしまうことも。たとえば、想定より受注が入りすぎて、一時的に資金が不足するケースも。そんなときに便利なのが「短期借入金」です。
■ 短期借入金は“資金の調整弁”
短期借入金は、枠の中で柔軟に借りて返せる仕組み。運転資金ニーズに対応するため、複数の現場で一時的にキャッシュが足りなくなったときなどに重宝します。副業的な現場が急に入って資金が動くようなとき、日々の資金繰りにメリハリをつけられるのが魅力です。
ただし、借入枠や返済計画とのバランスを考える必要があります。事業が不規則であるほど、短期枠の準備は極めて重要になるのです。
■ 人工応援売上と保証協会の注意点
建設業でよくあるもう一つの注意点が、この「人工応援による売上」です。人手が足りない現場にリソースを貸し、自社売上として計上するケースですね。しかし、これが“人材派遣”と見なされると、信用保証協会の保証対象外となる可能性があります。
つまり、売上の一部が保証対象として認められない=融資枠が縮小される可能性があるんです。そこで工夫が必要です。
対策方法のひとつとして、請求書の明細に「一式」と表記し、具体的に「人工」と記載しないという構成があります。さらに、決算書や試算表でも明確に「人工応援」とはせず、自社の収益のまま計上する。こういった運用上の配慮が保証対象として認められる鍵です。
■ 融資戦略は“長期借入+短期借入枠のハイブリッド”
まずは長期借入で初期の資金をクリアにしておく。その上で運転資金不足には短期借入金で対応。人工応援売上も保証対象から外れないよう配慮しつつ、自社収益として整理しておけば、保証協会枠の無駄な圧迫も回避できます。
■ 実例:融資枠と資金運用を組み替えて助かった会社A社
A社は初期に大型重機のために長期借入で資金調達しましたが、受注増加でキャッシュフローがひっ迫。一部の現場は人工応援による売上もあり、当初「保証対象外」との判断も検討されました。
そこで、当社では短期借入枠も併用し、人工応援売上については請求書を工夫。「〇〇工事一式」という表記に変更。決算書には明記せず、売上自体を自社収益として計上しました。結果、保証協会の審査にもパスし、無事に調達枠を確保。
資金繰りは安定し、次の受注も安心して対応できる体制が整いました。
■ 建設業のための資金調達チェックリスト
- 長期借入金で“設備や大型投資”を確実に対応
- 短期借入金枠は運転資金用として併用
- 人工応援売上の処理に注意:請求書に「一式」表記を
- 保証協会用の補足資料も請求書などでしっかり裏付け
- 月次で融資枠や現預金、売掛金、在庫を管理し、必要に応じた借入判断を
■ まとめ:柔軟に、賢く、資金調達を設計しよう
建設業では、融資は単なる「借りる」ことではなく、本質的には「現場を回し、受注に対応し続けるための仕組み」になるべきです。長期借入と短期借入を組み合わせ、人工応援売上にも抜け穴なく対応できれば、資金繰りは格段に安定します。
もちろん、融資や保証協会への対応は複雑です。当社では、建設業に特化した外部CFOとして、資金調達戦略や融資枠の使い方、書類整備までを支援しています。キャッシュフローの不安がある、融資枠をもっと活かしたい、といったお悩みなどあればお気軽にご相談ください。



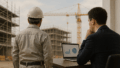

コメント